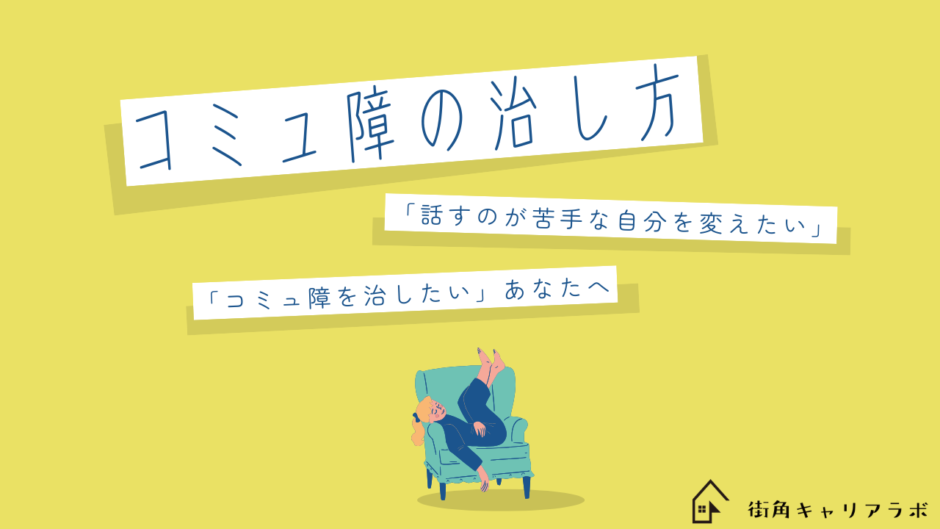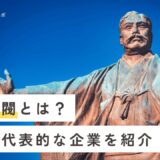人と話すのが苦手な方の中には、「自分はコミュ障だから」と周りとのコミュニケーションを諦めてしまっている方もいるのではないでしょうか?
実はコミュニケーションの苦手意識は、いくつかのコツをおさえることで簡単に改善できます。
そこでこの記事では、コミュ障の治し方の具体的な方法をまとめてご紹介!
「コミュ障を治したい」「話すのが苦手な自分を変えたい」という方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。
そもそも「コミュ障」とは
「コミュ障」とは、コミュニケーション障害の略称です。
コミュ障と略すのはインターネット上が始まりとも言われており、現代では日常生活の会話でもよく使われる俗語となっています。
コミュ障の特徴はいろいろありますが、ここでは主なものを簡単にまとめました。
以下の特徴に多く当てはまる場合、「コミュ障」の可能性が高いかもしれません。
コミュ障の特徴☟
- 人とコミュニケーションがうまく取れない
- 人と話すことや関係をもつこと自体が苦手
- 学校や会社で会話の輪に入れない
- 相手と話が噛み合わない
- 話しかけられてもどう返事したらいいかわからず言葉が出ない
- 人との距離感がうまく測れない
コミュ障は病気?診断がつく場合もある
俗語として使われる「コミュ障」には、明確な基準や診断などはありません。
しかしその一方で、医学的な診断が下りる「コミュニケーション障害」も存在します。
以下は、米国精神医学会が発行する「DSM-5-TR(精神疾患の診断基準・診断分類本)」に書かれている「コミュニケーション症群/コミュニケーション障害群」の疾患です。
● 言語症 / 言語障害
● 語音症 / 語音障害
● 小児期発症流暢症 / 小児期発症流暢障がい(吃音)
● 社会的(語用論的)コミュニケーション症 / 社会的(語用論的)コミュニケーション障害
● 特定不能のコミュニケーション症 / 特定不能のコミュニケーション障害
これらの疾患の症状に当てはまり、専門医師による診断を受けた場合は、医学的にコミュニケーションに障害があると言えます。
またこれ以外にも、発達障害・不安障害・パーソナリティ障害・知的障害・てんかん・社会不安症などでコミュニケーションになんらかの障害が起きていることもあります。
コミュニケーションにおいてあまりにも大きな障害を感じる場合は、医学的な観点から診察してもらうのも一つの手です。
コミュ障を治すコツ 〜マインド編〜
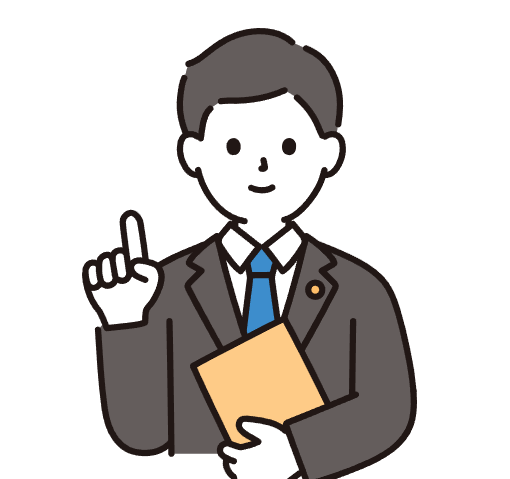
ここからは、医学的な診断名がつかない「コミュ障」を治すためのコツをまとめて紹介します。
人とのコミュニケーションに苦手意識を持っている方は、まずこちらのマインド編から参考にしてみてください。
人から見た自分を気にしすぎない
周りからどう見られているかを考えると、何をするにも緊張・萎縮してしまいます。
その結果、何を話したらいいかわからなくなり、コミュニケーションが余計に難しくなってしまうのです。
そもそも、他の人がどう思っているかをどれだけ考えても、それはあなたの想像でしかありません。
人から見た自分を気にしすぎず、他の人のことを考えてしまった場合はそれに気づいて考えを修正できるようにしましょう。
人に興味を持って接する
コミュニケーションを円滑にするには、相手に興味を持っていろいろ話をすることが大切です。
「会話が続かない」「何を話していいかわからない」とお悩みの方は、まず相手のいろいろな部分に興味を持つようにしましょう。
会話のキャッチボールを続けるには、相手の話に対して質問や疑問形で返すのがベスト。質問と言っても難しく考える必要はなく、少し気になることを気軽に聞いてみればいいのです。
相手に興味を持てれば、聞きたいことが頭に浮かびやすくなり、質問を会話もスムーズになります。
まずは興味を持てる相手や共通点がある相手を見つけて、相手の話に質問または疑問形で返すことを意識しながらコミュニケーションを取ってみましょう。
マイナス思考・完璧主義をやめる
コミュ障という自覚がある方によく当てはまる特徴が、マイナス思考です。
また、完璧主義でミスを許せない性格だと、一度コミュニケーションがうまくいかなかったことでマイナス思考に陥り、「自分はコミュ障だ…」と思い込んでしまいます。
しかし、人は誰とでも同じくらい仲良くなれることはほぼなく、コミュニケーションがうまくいかない経験は誰でも必ずあるものです。
人には合う人と合わない人が必ずいるので、もし失敗しても「合わない人に当たったんだな」と思い、考えすぎず次にいきましょう。
話すことを恐れない
コミュ障だと言う方の多くが、人と話すことにコンプレックスを抱いていることでしょう。
「もう失敗したくない」「人と話す時の雰囲気に耐えられない」と恐怖心を持っている方も多いかもしれません。
しかし、本来コミュニケーションに成功や失敗はなく、「相手がつまらなそうにしている」のもあなたの思い込みに過ぎない可能性もあります。
完璧なコミュニケーションというものは存在しないのですから、あまり難しく考えずに会話を楽しんでみてください。
たとえうまくいかなくても、必要以上に落ち込まず次にチャレンジすることが大切です。
コミュ障を治すコツ 〜実践編〜
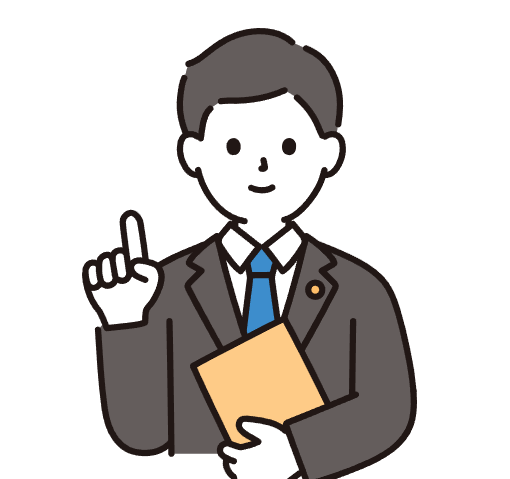
次は治すコツの実践編を紹介します。
コミュニケーションをより簡単にするコツをまとめているので、ぜひできるものから試してみてください。
挨拶を習慣化する
コミュニケーションの中で最も何も考えず、気軽にできるのが挨拶です。
まずは挨拶を習慣にし、コミュニケーションに対する苦手意識を少しずつなくしていきましょう。
また、いつも挨拶をしてくれる人には、多くの相手が好感を持つものです。
いつも挨拶しているだけでもコミュニケーションの糸口は広がるため、ぜひ積極的に行いましょう。
常に笑顔を心がける
笑顔は、非言語コミュニケーションとしてとても重要です。
当然ですが、いつも退屈そうだったり気難しそうな顔をしている人よりも、常に明るく笑顔で過ごしている人の方が話しかけたくなりますよね。
ただし、気持ちが沈んでいるときまで無理に笑顔でいる必要はありません。
まずはあなたのできる範囲で笑顔を心がけてみましょう。
話すときは相手の顔を見て相槌をうつ
相手の顔を見て、相槌をうちながら話を聞くと、相手に「ちゃんと話を聞いてくれているな」という印象を与えられます。
相手に好感を持ってもらうのは、コミュニケーションを円滑にする第一歩。
話すときには相手に身体を向けて、なるべく顔を上げながらしっかり話を聞いていることをアピールしましょう。
相手を褒める
挨拶や笑顔、話すときの姿勢が無理なくできるようになってきたら、次は会話の中で相手を褒めてみましょう。
褒めるのは、持ち物・服装・髪型など何でもOKです。
褒められて機嫌を悪くする人はほとんどいないので、純粋にいいなと思うものがあれば話題に上げてみてください。
コミュニケーションが重要な環境に身をおく
荒技ですが、コミュ障を本気で治したいと思うなら、コミュニケーションが重要な環境に飛び込むのもいいでしょう。
話すのが苦手という性格は、毎日たくさん人と会話する環境にいると自然に治っていることもあります。
これは人と話すことに慣れ、コミュニケーションの取り方が身についたためです。
コミュ障がなかなか治らず苦労している方は、ガラッと環境を変えてみるのもおすすめですよ。
コミュ障という思い込みを捨て、気軽に会話してみよう!
一般的に使われるコミュ障は、人見知りやそもそも会話が少ないなど、自分で改善できる可能性があるものです。
そして、コミュニケーションにはコツがあり、そのコツを意識して過ごすだけでも「会話が続かない」「何を話していいかわからない」という事態はほとんど避けられます。
「自分はコミュ障だから…」と殻を閉ざしてしまうのではなく、まずは簡単にできることから日常に取り入れてみましょう。
この記事で紹介した治すコツは明日から簡単にできるものも多いので、コミュ障を治したい方はぜひ参考にしてみてくださいね。
参照:LITALICO「コミュニケーション障害の特徴や原因は?症状や診断の種類についても解説」