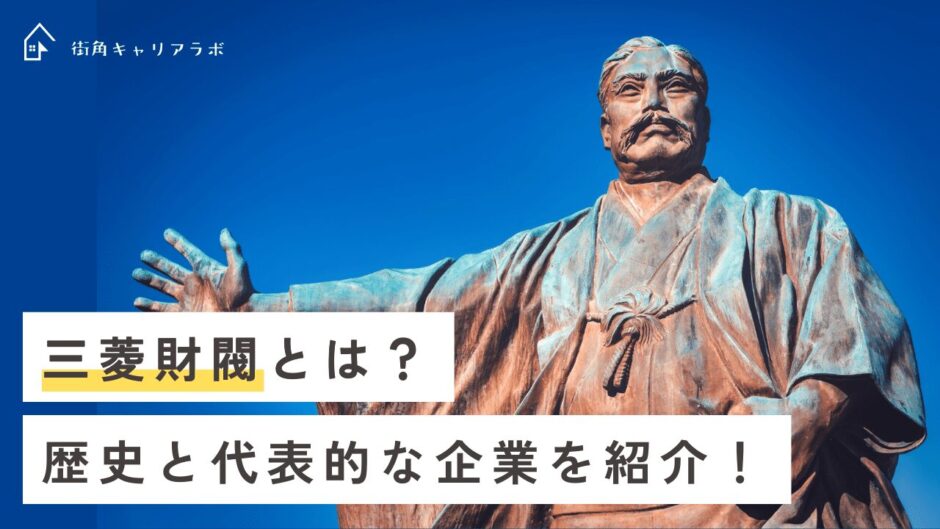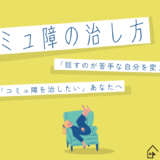就職先の企業選びを考える時の一つの考え方として、財閥系の企業に就職するというのが一つの選択肢となります。現代の日本では財閥は解体されていますが、三菱や三井、住友などの有力財閥から発展した企業には、現在でもその業界をけん引する代表企業が多数存在します。
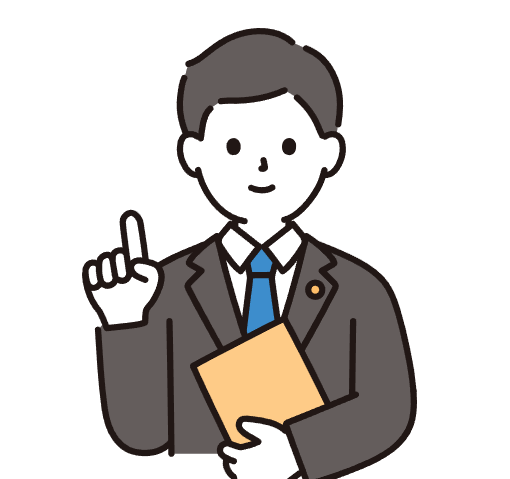
今回はその財閥の中でも強力な企業グループを形成している三菱財閥の歴史と、代表的な企業について紹介していきます。
三菱財閥として存在していた第二次世界大戦までの歴史

「財閥系」という呼び名はいまの就職活動でもしばしば用いられますが、実は正式な財閥は解体されて既に70年以上が経過しています。まずは、三菱財閥が成立して発展、解体するまでの歴史をまとめました。
三菱財閥の成立
三菱財閥の創始者は土佐生まれの「岩崎弥太郎」という人物です。彼は開成館長崎商会において、24歳で実現した長崎出張の経験を活かして、欧米商人とのリレーションや取引を開拓していきました。当時、開成館は土佐藩の欧米商人との窓口として機能していたのです。
その後、明治政府が藩営事業を禁止しようとしたため、九十九商会を設立、藩の船を買い受けて海運事業を始めようとしたときに「三菱商会」として海運と商業を主軸に事業展開することに。この頃にいわゆる「スリーダイヤ」の三菱のロゴも使われるようになっています。なお、このロゴのルーツは諸説ありますが、岩崎家の家紋『三階菱』と土佐藩の船についていた山内家の家紋『三ツ柏』を組み合わせたものといわれています。
三菱財閥の拡大
その後、海運事業が拡大する中で「郵便汽船三菱会社」という名前に改称。順調に事業を拡大し、日本・上海航路など海外航路も開拓していきます。また、1877年の西南戦争での軍需輸送で莫大な収益を獲得しました。しかしその後、海運における三菱の独占状態に批判があつまるなかで、半官半民で設立された共同運輸との競争が激化しました。両者の過当競争を問題視した政府が、両社を合併させて、日本郵船を設立。設立当初は「三菱が海運事業を失った」という見方もありましたが、数年のうちに実験を回復したため、現在のところ日本郵船は三菱財閥系企業の代表企業の一つとなっています。
また、海運が打撃を受ける間に、譲り受けた官営長崎造船所を拠点に造船業に乗り出します。1900年に入ると、造船業に航空機製造などを統合する形で「三菱重工業」として発展していきます。(そのため三菱重工業の祖業は「造船」であるとしばしば紹介されます)なお、1885年には第百九国立銀行を買収し、三菱銀行の前身として銀行業へ、87年には東京倉庫を設立して倉庫業も始めています。
1893年に商法が施行されると、三菱合資会社という名前で改組。その後さらに多角化を進めます。1910年代には分社化を進め麒麟麦酒(キリンビール)、三菱商事、三菱鉱業(三菱マテリアルの前身)、三菱銀行、三菱電機など現在の日本の代表企業(もしくはその前身)が次々立ち上がっていきます。昭和初期までの日本の経済発展をけん引した一方で、軍事力の発展にも寄与したため、後にGHQに「財閥が軍国主義を支えた」との疑念を持たれることにもなりました。
財閥解体
世界大戦が終結するとGHQは財閥によって一部の有力者が日本の産業を支配していて「財閥が軍事国家を形成する原因となった」との見方を示しています。財閥と日本の軍事化の因果関係は不明確ではありますが、このような方針の下、日本の財閥は解体させられることになります。
三菱本社、三菱商事が解散し、その他の各三菱財閥系の企業も分割化されました。また、各社の有価証券について持株会社整理委員会を通じて実質的に政府が保有することとなります。一時政府が保有することになった株式は証券処理調整協議会を通じて市場に売却されました。
旧三菱財閥の結束と企業の発展

このように三菱財閥は第二次世界大戦が終結したタイミングで解散されました。その後正式に「三菱財閥」が再結成されることはありませんでしたが、いくつかの企業はかつての影響力を取り戻すほどに発展し、また業種の三菱系企業間での結束が次第に強まっていきました。
旧三菱財閥の再集結
1949年には一時「三菱」をはじめ旧財閥名の使用自体を禁じる案も出ていましたが、結局この案はすぐに廃止されたため、現在でも多くの三菱財閥系企業が「三菱」を冠して経営されています。折しもこの頃から、旧三菱財閥系企業の再集結が進められることとなりました。
最初に進められたのは不動産でした。現在の三菱地所に当たる事業は、1950年当時関東不動産と陽和不動産に分割させられていましたが、このうち陽和不動産の経営権が第三者に奪われそうになるという事件が発生。これをきっかけに再統合の機運が高まりました。
1953年に両社が三菱地所として合併し、丸の内一体の一等地を開発・管理する不動産ディベロッパーとして発展していきます。また翌年には後に総合商社に発展する三菱商事が130社のグループ企業を合同させて再結成します。1964年には三菱重工業の再結成も達成しました。
金曜会と三菱財閥系企業の結束
1954年には三菱主要企業の親睦・情報交換を目的とした金曜会が補足。従来の「財閥」としての組織はなくなりましたが、各業種の代表企業の対等な関係で成り立つ企業グループが形成されました。以降、バブル崩壊期まで原材料や流通ルートなどにおいて三菱系の企業を優先的に購入・利用したり、財政面において互いに融通し合ったりというような動きも見られ、金曜会を軸に三菱グループ一体となって各産業で企業が発展していきました。
また、財閥という組織がない中で「株式の持ち合い」が財閥系企業の結束を強める効果を持ちました。持ち合いとは株式本来の目的である企業の成長や株価上昇による利益を追求する投資ではなく、お互いの連携関係を強めるために政策的に二社間でお互いの株式を持ち合うものです。
1990年代頃までは多くの企業が盛んにおこなっていましたが、特に同族の財閥系企業間では盛んにおこなわれ、旧財閥の結束を維持する効果をもたらしていました。
財閥の結束は従来より弱まっているという見方も
戦後にかけても実質的には維持されてきた三菱財閥の結束ですが、一部では金融自由化や企業経営の透明性を求める機運の高まりなどを背景に、結束は弱まっている部分もあります。特に顕著なのは株式の持ち合いです。
株式市場の発展という側面からみると、株式の持ち合いは株の自由な流通を阻害するものなので必ずしも望ましいものではありません。金融のグローバル化が進み、日本独特のシステムである株式持ち合いに批判的な意見も高まっている中、近年は株式の持ち合いを解消する動きが進んでいます。
また、同財閥企業間での優遇取引も自由競争の観点からは望ましいものではありません。企業経営の視点でも、より優れた企業との取引を阻害して経営が非効率になる恐れがあります。そのため、近年では三菱財閥間の取引を表立って優遇することはなくなっています。
三菱財閥系の代表企業

三菱財閥を起源とする企業は多岐にわたる業種に存在し、多くの業種においてリーディングカンパニーや最大手企業の一角に成長しています。ここからは三菱財閥系の代表的な企業を簡単に紹介していきます。
三菱商事株式会社
三菱グループの中核企業の一つであり、三菱財閥の直系企業のひとつです。他の財閥系商社などと共に五大商社の一角を形成しています。
総合商社として幅広い業種でビジネスを展開していて、石油、ガス、金属、化学品、食料品、機械、自動車、航空機など、多岐にわたる商品の卸売りや開発、時には小売に至るまでバリューチェーンの川上から川下まで様々なビジネスに参画しています。
三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG)
前身の三菱銀行が三和銀行、東京銀行、UFJ銀行など複数の金融機関の合併を経て成立した金融グループです。現在では銀行、証券、信託銀行など多岐にわたる金融サービスを提供しています。世界最大級の資産を持つ金融グループの一つであり、国内外でサービスを展開しています。2021年には国内の金融機関で初めて、カーボンニュートラルを宣言したことでも話題になりました。
東京海上日動火災保険株式会社
「三菱」の名前はついていませんが、実は三菱グループの中核企業の一つで、火曜会にも入っています。1879年に東京海上保険会社として創業し、合併・統合を経て現在の形に。日本国内のみならず、世界各地に支社・代理店を持ち、海外事業にも力を入れています。
現在では火災保険・自動車保険・損害保険などの損害保険事業、その他企業のリスクマネジメントや海外旅行保険など幅広い保険商品を提供しています。地震保険でも業界トップクラスのシェアを誇っています。祖業にあたる海上保険ビジネスも継続しています。
三菱重工業株式会社
航空機、宇宙ロケット、船舶、エネルギー関連機器、機械、鉄道車両などの製造メーカーです。元々は造船から始まった企業ですが、近年はエネルギー施設のおよびプラントの重工開発の比率が高くなっています。原子力発電所やLNGタンカーの建造など、エネルギー分野の大型プロジェクトにも参画。また、売上への寄与は高くないものの宇宙ロケットなどの先進技術の開発にも積極的です。
キリンビール株式会社
キリンビールは、1885年に創業された日本の醸造会社で、もともとは「麒麟麦酒」という表記でした。横浜で創業されましたが、すぐに東京に本社を移し、国内外に事業を展開しました。現在、キリングループは、ビールやワイン、ウイスキー、食品、医薬品など、多岐にわたる事業を展開しています。同じくビール系大手のアサヒと同様に、海外比率が高く、海外売上比率が50%を超える年もあります。
日本郵船株式会社
日本郵船は三菱財閥を成長させる原動力となった企業です。また、日本でみても最古の船舶運輸会社の一つで、日本の国際海運産業を牽引してきました。1885年の創業後すぐに海外航路開拓に乗り出し、現在ではグローバルな海運物流を担っています。また、液化天然ガス(LNG)輸送船や石油タンカーなどの運航でも重要な役割を果たしており、世界的な物流企業の一つとなっています。
三菱マテリアル株式会社
三菱マテリアルは、現在では三菱グループの非鉄金属加工などを手がける製造会社の一つですが、源流の三菱鉱業は炭鉱をはじめとした鉱山開発を手がける企業でした。そこに金属やセメント加工の企業が合併する形で現在の形となりました。
特殊鋼や非鉄金属、セラミックス、エンジニアリングプラスチックスなどの製品を扱っています。日本有数の素材メーカーであり、自動車産業、電子産業、航空宇宙産業、エネルギー産業など様々な分野の原材料を提供しています。
三菱系には日本有数の大企業が連なる
まとめ
江戸末期から発展した三菱財閥は、発展・解体・再結集を経て、現在に至ってもその関係性は続いています。株式の持ち合い解消など結束が弱まっているとの見方もありますが、各社が各産業を代表する大企業としての地位をすでに確立しており、その立ち位置が簡単に揺らぐことはありません。
日本を代表する大手企業への就職にチャレンジするなら、三菱財閥系企業に着目してみるのもよいでしょう。