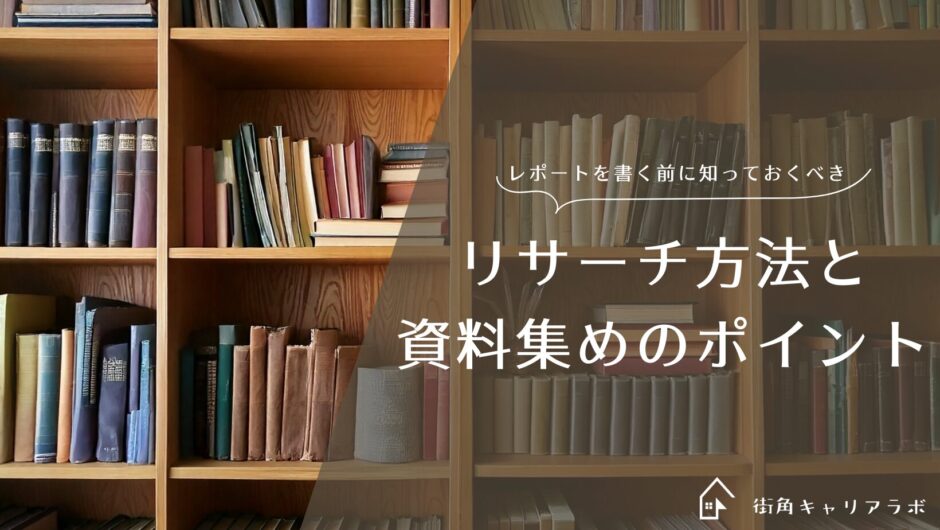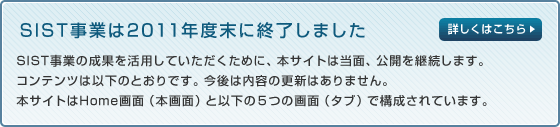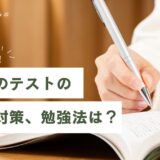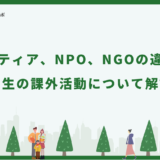「レポートの書き方が分からない!」「資料はどうやって集めれば良いの?」多くの大学生が、テスト前になって急にこのように焦りだしたこともあるのではないでしょうか。今回は、大学生が使える、レポートの書き方と、そのためのリサーチ方法・資料収集の方法について紹介します。リサーチ法について知ることで、レポートの質を高めるだけでなく、関心のある分野についての理解を深めていきましょう。また、様々なリサーチ方法を組み合わせ、蓄積して、自分なりの研究方法を確立していきましょう。
レポートの組み立て方(書き始める前段階)
まずは、レポートはどのように構成すべきかについて説明します。レポートの基本的な要素ごとに進め方を紹介していますが、人によって、順番や、細かい方法は異なります。各ステップを何度も行き来して、主題を変えながら研究を進める人もいるでしょう。また、最終的に結論が出なかった仮説などを、レポートでどの程度写実的に説明するかは、分野にも依拠することを留意しておきましょう。
主題・目的の決定
まずは、レポートの主題(扱うテーマ)と、レポートを書く目的(何のためのレポートなのか)を決定します。これらはイントロダクションで明記するのが一般的ですが、レポート全体を通して扱ったり、触れたりしていくものでもあります。レポートの核となる部分なので、書き始める前に明確にしておきましょう。特に、目的については、「課題を終わらせるため」などではなく、どのような学術分野の理解を深めるためのレポートなのかを意識して決めましょう。
リサーチ方法の確定
次に、リサーチ・調査方法を決定します。リサーチ方法の種類については後述の通りですが、様々な調査方法がある中で、自分の主題を深堀したり、仮説を証明したりするために適している方法を選ぶ必要があります。また、複数のリサーチ方法を組み合わせることも効果的でしょう。
資料集め
続いて、決定したリサーチ方法に沿って、資料集めをする必要があります。資料を集める段階では、この段落の最後に述べる、「引用・出典」時に困らないように、参考にしたすべての資料情報を記録・保存しておく必要があります。その場合には、オンライン図書館や大学のデータベースなどによく見られる、著作物情報をまとめた書誌や、参考文献を蓄積できる文献管理ツールが有効です。大学によっては、生徒に無料で提供している参考文献の管理ツールが存在するので、自分の大学のメディアセンターなどに足を運んだり、ウェブサイトを訪ねたりして、確認しておきましょう。
仮説決定
次は、仮説決定です。資料を集め、リサーチする中で、主題に対する仮説が浮き上がってくると思います。主題に沿った大きな仮説と、その仮説を証明するためのサブ的な仮説など、複数あっても良いでしょう。仮説のない、まとめ・要約的なレポートもあると思いますが、論点を明確にし、議論を充実させるためには、仮説があると便利です。ただ、仮説を決定してから、証明するために、再び前のステップの「資料集め・リサーチ」に戻る必要性も出てくると思うので、二つのステップは再帰的に行うことを心がけると良いでしょう。
レポートの組み立て方(書き始める段階)
主題を決め、リサーチや資料集めを行い、仮説が決まってきたら実際に書いていくことができます。ここではその手順をご説明します。
仮説証明と結論
これらのステップを経て漸く、レポートを書くことに着手できます。設定した仮説に対するYESとNOの立場両方から論じることが、レポートの質を高める秘訣です。一方で、ある程度結論を出す必要はあるので、両者の立場の比重は考えた方がよいでしょう。ここで必要な視点としては、「仮説を証明できなかった」という結論でも充分であるということです。一般的に、レポートの目的は、リサーチを行う中で主題に対する理解を深めることと、深まった理解の報告なので、仮説証明にYESと答えることが求められているわけでは必ずしもありません。
考察
結論を導き出した後は、考察を述べる必要があります。考察は、調査過程やレポート自体の限界や、批判点などについて論じるとよいでしょう。例えば、人の記憶についての実験を行って書いた心理学のレポートであれば、実験対象者の社会的属性における偏りなどが考察として挙げられるでしょう。また、考察で、今後更に拡張できる議論や調査について論じるのも一つです。
引用・出典
最後に、非常に重要なのが引用と出典の明記です。先述したように、資料集め・リサーチの段階でレポートの参考とした著作物と、レポートとの関係性は明確に示さなければなりません。他の著作物で使われていた文章やデータ、語句などを用いる場合は、引用が必須です。「」やインデントを利用して、はっきりとどこの部分が引用なのかを示しましょう。
また、出典情報については、大学・分野・科目で推奨されている出典を示す方法(APAやSIST02など)に則って、著作物の情報を記述しましょう。レポートの最後に参考文献のリストを示す方法や、ページの下部に補足情報として記す方法などがあります。
引用と出典が明記されていないと、剽窃として扱われ、単位不取得や、退学などの処分を受ける場合があるので、十分注意しましょう。
APA方式(American Psychological Association)
APA方式は、主に心理学や社会科学分野で広く使われている引用スタイルです。
本文中の引用例:
- 1名の著者の場合:「佐藤 (1954) によれば… 」/ 「…が報告されている (佐藤, 1957)」
- 2名の著者の場合:「…した(佐藤・田中, 2023)」
- 3名以上の著者の場合:「…した(佐藤・大森・山田, 2023)」(初出時)、以降は「…した(佐藤ほか, 2023)」
参考文献リストの記載例:
- 書籍:佐藤太郎 (2023). 『学術論文の書き方』. 東京大学出版会.
- 雑誌論文:佐藤太郎・田中花子 (2023). 大学生のレポート作成に関する研究. 『教育学研究』, 45号, pp123-135.
- ウェブサイト:総務省 (2023). 「社会調査の方法」. https://www.soumu.go.jp/example(参照2025年5月1日)
(参考:東京女子大学 現代教養学部 心理・コミュニケーション学科 コミュニケーション専攻thesismanu資料2022改)
SIST02方式(科学技術情報流通技術基準)
SIST02は、日本の科学技術振興機構(JST)が定めた引用スタイルで、主に自然科学系の論文で用いられます。
本文中の引用例:
- 引用箇所の末尾に上付き数字で示す:「…という研究結果がある¹⁾」
- または、著者名と引用番号を併記:「佐藤¹⁾によれば…」
参考文献リストの記載例:
- 書籍:1) 佐藤太郎. 学術論文の書き方. 東京: 東京大学出版会; 2023. 234p.
- 雑誌論文:2) 佐藤太郎, 田中花子. 大学生のレポート作成に関する研究. 教育学研究. 2023, vol. 45, no. 2, p. 123-135.
- ウェブサイト:3) 総務省. “社会調査の方法”. https://www.soumu.go.jp/example, (参照 2023-05-01).
リサーチ方法・資料収集
次に、リサーチ方法・資料収集の方法について詳しく紹介します。調査方法(リサーチデザイン)自体を研究している研究者もいるほどなので、全てはカバーしきれませんが、大きく三つの方法について説明していきます。
先行研究の利用
まずは、先行研究として既に研究されている知識・議論を集める方法があります。科学分野など、発見物が体系的に蓄積されている学術分野においては、非常に重要なステップであるといえます。自分の興味のある分野がどの程度研究されており、どこが研究されていないか、などの全体像を掴むためにも、先行研究についての知識を得る必要があります。
実際に先行研究を利用したい場合には、まず、検索エンジンの利用が挙げられます。ただし、Googleなどの一般的な検索エンジンをただ利用するだけでは、表層ウェブという、スポンサーがついているなどの理由で検索に引っ掛かりやすい情報のみを取得することになりかねません。そのため、大学のメディアセンター(図書館)や、電子書籍が存在するデータベースなど、他の情報取得ツールも利用する必要があります。特に、大学機関の多くは、所属している生徒のみアクセスできる情報システムを保有しています。それぞれのアルゴリズムがあるので、ぜひ一度、自分の大学にはどのようなメディアが存在し、どう活用できるのかを知る機会を持つことをおすすめします。大学のメディアセンターを訪ねてみるのも良いでしょう。大学のメディアセンターやデータベースでも手に入れられなかった情報でも、国立図書館に行くとアクセスできる場合などもあるので、様々な場所に拠点を持っておくのも有用です。
量的調査
次に紹介するのは、量的調査です。量的調査とは、アンケートやサーベイなど、数字やデータを統計的に扱う調査です。変数の設定などを定量的に行い、それらの関係性を調べます。大量の人を調査対象とする場合が多いです。量的調査の結果の多くが、数値化されるため、結論がグラフなどで可視化されやすいうえ、先行調査の蓄積を利用できるところが利点であると言えます。視点の取り方を変えれば、同じ量的調査から、異なる結論を導いたり、統計学の知識があれば、変数をいじって結論を出すこともできるため、費用や時間の削減にもつながります。しかし、量的調査においては一般化する機能を禁じ得ないため、既存の枠組みに当てはまらない、いわゆる「外れ値」などが見落とされる可能性が高いとも言えます。
質的調査
一方で、量的調査と相反する位置づけにあるのが質的調査です。質的調査には、インタビューやオーラルヒストリー、参与観察などがあり、科学的な証明を必ずしも目的としていない、定性的な情報を扱う調査です。そのため、調査対象者の数は問題ではなく、一人の語りから一つの結論を導き出すことも可能です。利点の一つは、量的調査で取りこぼされる「外れ値」に着目し、調査を行うことで、新たな枠組みや変数、仮説を生成することができる点です。そのため、特にマイノリティ研究に利用されることが多いです。一方で、時間や費用が非常にかかることが問題の一つです。例えば、インタビューを行う際は、時間はもちろん、インタビュー相手と会うための交通費や、心理的負担なども鑑みると、学部生が継続的に行うのはなかなか難しいともいえます。
(参考:社会調査の方法https://www.soumu.go.jp/main_content/000819731.pdf)
今回は、レポートの書き方と、その中でも資料集め・調査方法について紹介しました。最後の段落で紹介した三つの調査方法については、自分なりに組み合わせていくことで、新しい学術的な枠組みを生み出すことができるでしょう。多くの大学で、卒論が必須であるという点では、大学生は研究者の卵とも言えます。調査をしたり、調査報告としてレポートを書いたりするなかで、研究者の卵として自分の興味分野への理解を深め、既存の知識に捉われない批判的な視点を養っていきましょう。