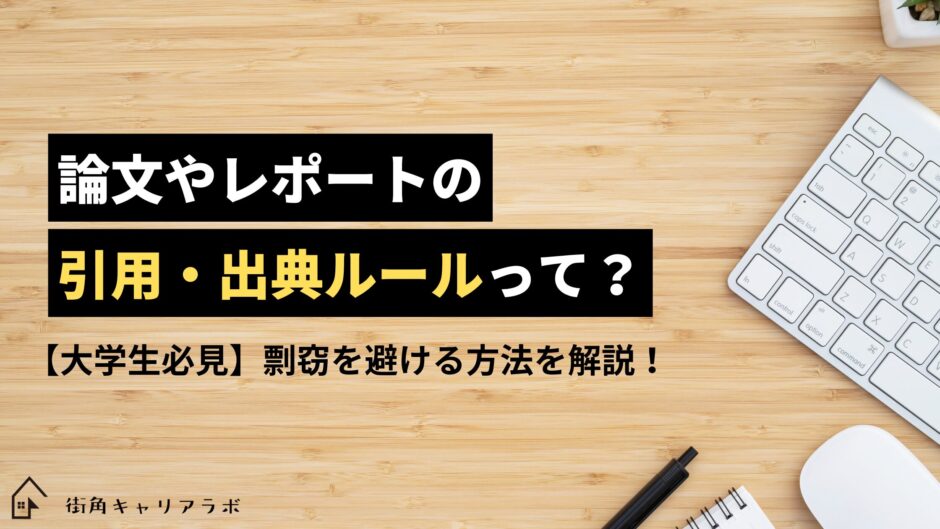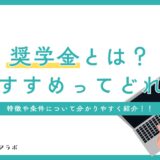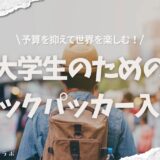大学生活において避けて通れない”論文・レポート”。しかし誤った方法で作成してしまうと、思わぬ重大な処分を受けることもあります。この記事では剽窃の意味や引用、出典の利用について解説。適切な引用と出典のルールをしっかりと身につけ、今後の資料作成に活かしていきましょう!
剽窃(ひょうせつ)・プラジアリズムとは
基本的に剽窃とプラジアリズムは両方とも「他人の言葉、文章、アイデアなどを自分のものとして発表すること」。プラジアリズムはラテン語の “Plagiarius”(子供の誘拐者)から来た言葉であり、剽窃もプラジアリズムも同義語として扱われることが多いです。
剽窃とは、他人のアイデアや文章を自分のものとして発表することです。一方、著作権侵害は法律違反です。例えば作者が著作権を放棄していて著作権侵害に当たらない場合でも、出典を明記せずに使えば剽窃になる、ということです。混合しがちですが、剽窃と著作権侵害は別物なんですね。
・正確に評価するため
レポートや論文は、あなたの能力を評価するためのものです。他人の考えを自分のものとして出してしまうと、正しい評価ができません。
・読者への情報提供
引用や出典を明記すると情報の信頼性を確認できるため、内容の説得力が増します。また関連する他の資料を見つけやすくなります。
では、具体的に何が剽窃にあたるのでしょうか?2つの事例をもとに説明します!
どんな行為が剽窃に当たるの?
引用や出典情報が記されていないのに、他人の文章・言葉・データ・アイデアなどを自分の成果物に含める場合です。ここで注意が必要なのは、アイデアを無断で使うのも剽窃に含まれるという点です。例えば、大学の論文やレポートに ”仮説として” 他の人にすでに提示されたことがある論を使う場合にも、必ず出典を明記しましょう。
他の人の考えやアイデアを自分のレポートや論文に使うとき、たとえ言葉を変えていても、出典を明記する必要があります。文章をそのまま使わなくても、内容を借りる場合は引用と出典情報が必要です。これがないと剽窃になってしまいます。
生成AI利用時の注意点
特に最近気をつけたいのがChatGPTなどの生成AIの使い方です。生成AIはネット上の情報を書き換えて提示するので、AIが作った文章をそのまま使うと、知らず知らずのうちに他人のアイデアを無断で使うことになります。これも剽窃になるので注意しましょう。
生成AIの使い方については、大学や学部、科目ごとに異なるルールが作られ始めています。自分の所属する学部や受講している授業でどのようなガイドラインがあるか、必ず確認しておきましょう。
もし剽窃が行われてしまったら?
実際に剽窃を行うと何が起きるのでしょうか。剽窃を行う側と剽窃の被害に遭う側それぞれにとっての悪影響を紹介します。
剽窃をした側への影響
大学生が剽窃をした場合、剽窃自体は法律違反に当たらないものの、大学では厳しく罰せられます。著作権侵害に当たらなくても、学問的な不正行為として扱われるのです。
また教授や博士の地位を得ている人が行った場合も、過去の剽窃が明るみに出るとその地位を失うケースもあります。学問の世界では信頼が最も重要な財産なのです。
大学によって処分は異なりますが、一般的には以下のようなものがあります
・課題や試験の単位不認定
・実名の公開
・最悪の場合は退学処分
特に深刻なのは、実名公開の処分です。実名が公開されてしまうと、大学での評判が落ち、教授や同級生からの信頼を失います。また、インターネットやSNSが広がる現代、不正行為の記録はオンライン上に残り続けます。今後の就職活動や研究機会に長期的な影響を与えることも考えられるでしょう。
剽窃被害を受けた側
更に、剽窃の被害を受ける著者にも多大な不利益が存在します。
研究の世界では、誰かの研究を引用することは、その研究の価値を認める大切な行為です。実際に、研究者の評価は「引用回数」で測られることも多く、「引用栄誉賞」という、多くの研究者から引用された優れた研究に対する賞も存在します。
そのため剽窃が行われると、原著者には次のような不利益が生じます。
・本来評価されるべき研究が正当に引用されず、評価の機会を失う
・引用回数が増えないため、研究者としての実績に影響する
・自分の研究が無断で改変され、本来の意図と異なる形で使われる可能性がある
剽窃は単なるルール違反ではなく、研究者コミュニティ全体の公正さを損なう行為です。他の研究者の貢献を正しく認め、敬意を示すことは、学問の発展にとって不可欠です。
だからこそ、剽窃を防ぎ、適切な引用を行うことは研究の誠実さを守るために重要なんです。
(参考:日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC094810Z00C22A8000000/)
剽窃を防ぐには?
最後に、剽窃を防ぐための方法について紹介します。剽窃のセルフチェックや適切な出典・引用ルールをマスターして、不安なく学生生活を送りましょう。
論文やレポートを書き終わった後にまずできるのが、剽窃をしてしまっているかかどうかのセルフチェックです。検索をかけると似たような文脈の情報源を洗い出してくれるので、それをもとに出典や引用を記したり、別の言葉に変えたりすることができます。
Google DocumentやWordなどの剽窃・プラジアリズムチェック機能付きアプリや、追加できるプラットフォームがおすすめ!
基本的には、著作名、著者や出版元、出版年、媒体名などの情報を明記しましょう。大学や教授、分野や媒体ごとに推奨している形式が異なる場合もあるため、出典や参考文献の記し方のチェックは忘れずに。
次に引用についてですが、元の文章をそのまま正確に引用する直接引用と、元の情報を要約して引用する間接引用があります。どちらの場合も「」やインデントを用いて引用箇所を明確に示し、情報元の著作名や論文名などを明記する必要があります。また、自分の論文やレポートにおいて、引用部分はあくまで補助的な要素にとどめるように留意しましょう。
まとめ
今回は大学生活に必須である剽窃についての知識を取り扱いました。剽窃は、加害者側にも被害者側にも不利益であることが分かったと思います。一度の出来心で、剽窃を行い、単位を全部落としてしまうなどということがないように、積極的に引用と出典情報の明記を行っていきましょう。
最後に。多くの大学教員は剽窃チェックツールを使っているので、剽窃をすれば必ずバレます。絶対にやめましょう!!