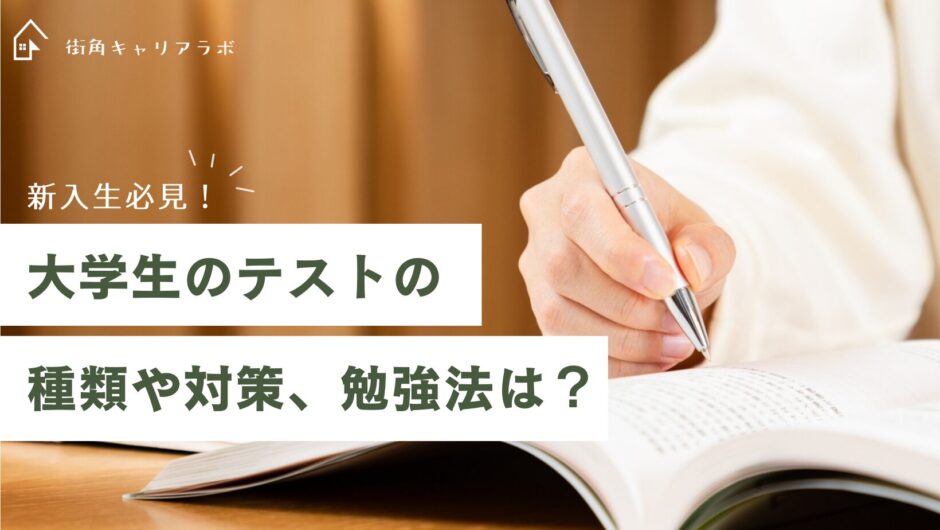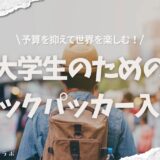大学入学したけど、成績が不安…。大学のテストは高校とどう違うの?
新入生の皆さんの多くがこれらの不安・疑問に悩まされていると思います。この記事では、一般的な大学のテストに関する年間スケジュール、テストの種類や種類別の対策などについて解説します。高校の時とは違うテストの様式や勉強法をしっかり把握し、効果的なテスト対策に繋げましょう。勉強面で安心できるようにすることで、インターンやバイトなど、課外活動にも力を入れられる、充実した大学生活が送れるはずです!
大学生のテストとは?

まずは、高校のテストとの比較や、実際の大学生のテストにおける詳しい種類や対策法への理解を通し、大学生のテストはどのようなものなのか知っていきましょう!
高校の定期テストと聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。直前の詰め込みや、大量の暗記など、苦い記憶が蘇る方も多いと思います。一方で、大学のテストにはレポート試験や持ち込み試験など様々な形式、期間があります。また、基本的に授業ごとのテスト実施・成績評価となるため、多くの大学で統一したテスト期間は明確に定められていません。
次に、大学のテストにおける様々な形式を紹介します。先述したように、基本的には「座ってテストを受ける」だけだった高校のテストと違い、大学ではいわゆる「テスト」の形を取らない評価形態もあります。また、各種類のテストに特有の、効果的な対策はどのようなものかを知り、テストに不安なく備えられるようにしましょう。
まず一つ目に、よく見られる評価方法として、課題提出による評価があります。
名前の通り、事前に設定された課題を期日までに提出することで成績がつきます。課題の設定は、シラバス配布の際に既にされているものから、最後の授業で言われるものまで様々あり、教授によって異なるので、いつ設定されるかをしっかりと把握して授業に参加する必要があります。
課題の形式としても、記述式のレポート、図式のもの、アンケート形式などいろいろな種類が予想されますが、基本的には授業内容をしっかりと理解できているかを測るものとなっています。そのため、対策としても、理解できなかった授業内容をそのままにしておかない、授業中に教授の要点をメモしておくなど、ベーシックなことが必要になります。加えて、質なのか量なのか、要約なのか考察なのかなど、課題の評価基準も早めに確認しておくと良いでしょう。
期日を守らずに提出した場合は、減点、もしくは採点さえしてもらえない場合もあります。締切に余裕を持って課題に取り組むようにしましょう。万が一、締め切りに間に合わないようなら、それが分かった時点で教授に相談するようにしましょう。
次に、大学特有ともいえる、出席・授業参加による評定について説明します。これは、授業への出席率や、授業で行われる議論、発表、グループワークなどへの参加度によって成績が決められるシステムです。高校ではほぼ見られない形式と言って良いでしょう。
しかし、出席や授業参加をしておけば良いだけではありません。出欠の取り方や参加度の測り方も授業によって異なることを心に留めておきましょう。特に、出欠確認のタイミングには様々あり、入室時の場合もあれば、「何分後」と決められていることもあります。また、出席票を紙で提出させたり、オンラインのフォーム提出だったり、点呼だったり、毎授業の課題提出で出席を確認されたりと、方法も多様です。
出席・授業参加の評価基準が様々存在することを鑑みると、高評価を得るためには評価方法の把握が最も重要な対策法だといえるでしょう。
続いて、最も高校のテストに近いのが、 試験結果による成績評価です。形式としては、着席・筆記型のものもありますが、コロナ後はオンラインでの試験も増えてきています。オンラインでの試験については、大学側からカンニング防止のガイドラインが出されていることも多いので気をつけましょう。
また、高校の時と違って、試験範囲が明確に示されていないこともあります。「授業で習ったこと」など大まかにしか言われない時もあるでしょう。しかし、そんな時に多いのが、授業中に教授がはっきりと「ここは試験で出題する。」と言ってくれる場合です。他にも、教授に個別に聞きに行けば、出題の概要を教えてくれる場合もあります。
そのため、対策としては、教授の発言に注意すること、躊躇わずに質問しに行くことなどが挙げられます。また、最後の段落で詳しく扱う、「過去問をもらう」ことも有効です。
テストを含めた大学生の年間予定

大学の大学のスケジュールは、いくつ学期が設定されているかによって変わります。また、各大学によって細かい予定は異なることも留意しながら、この記事では多くの大学が適用している2学期制(前半後半に分かれていれば4学期制)と3学期制について扱います。
| 期間 | テスト | |
| 春学期 | 4月~9月末 | ①5月末 ②7月中旬~月末 |
| 秋学期 | 10月~2月末 | ①11月中旬 ②1月末 |
ここでは、2学期制大学の大まかな試験スケジュールを紹介します。2学期制とはいえど、1学期につき前半後半があり、年間4回試験がある大学では、4学期制(クウォーター制)とされることも増えてきました。
1学期目は4月から夏休みを挟んで9月末までです。まず、4月入学・1学期授業開始から始まり、5月末にまず1学期前半科目(学期の前半のみ授業がある科目)の試験があります。
続いて、7月の中旬から末にかけて1学期科目(1学期中ずっと開講されていた科目)・1学期後半科目(学期の後半のみ授業がある科目)の試験があります。
夏休み後は、10月上旬から2学期がスタートし、3月の春休みまで続きます。2学期前半科目の試験は11月中旬に行われます。冬休みを挟んで、1月末から2学期科目・2学期後半科目の試験があります。
(参考:慶應義塾大学 https://www.students.keio.ac.jp/com/class/schedule/academic-calendar.html)
| 期間 | テスト | |
| 1学期 | 4月~8月中旬 | 6月中旬 |
| 2学期 | 8月下旬~11月末 | 11月中旬 |
| 3学期 | 12月~3月下旬 | 3月上旬 |
次に、3学期制の年間予定を説明します。3学期制は、履修の選択肢が多く、その時の興味によって履修科目を細かく変更しやすい、リベラルアーツの大学で多く適用されています。
1学期は4月から8月中旬まで、2学期は8月下旬から11月末まで、3学期は12月の頭から3月下旬までです。それぞれ、6月中旬、11月中旬、3月上旬に試験が行われます。
(参考:ICU https://www.icu.ac.jp/about/calendar/)
大学テストの対策方法

ここまで、テストの種類や種類別の対策方法、年間スケジュールなどについて見てきましたが、この段落では、どのテストにも共通する、大学生のテストならではのテスト対策方法を紹介します。
まずは、テストの過去問を活用した対策方法です。教授の一部には、毎年同じ授業を開講している人もいます。その場合の多くでは、テストで例年似ている問題が出題されます。
先輩などにお願いして過去問をもらい、演習を重ねることで、テストに向けて戦略的に備えましょう。
次に有効的なのは、同じ授業をとっている人と一緒に勉強することです。当たり前のように聞こえるかもしれませんが、大学での勉学においては、一緒に勉強することに大変効果があります。
特に人文系分野の科目では、批判的な視点・思考が評価されることが多く、様々な人の考えを知り、議論を深めてテストに臨んだ方が、出題に対する自分なりの議論を展開しやすいからです。
もちろん、他人の課題をコピーする剽窃には十分注意すべきですが、視点を共有し、一緒に考えることは、知識だけでなく理解を深めるのに必要です。加えて、過去問や教授が発言していたことなど、1人では取りこぼしてしまいやすい情報を共有できるという面でも、同級生と一緒にテスト対策をすることは効果的であると言えます。
最後に、基本的ではありますが、テスト対策において、最も重要と言って良いのが、評定・成績が何によって決まるのか明確に把握することです。例えば、「課題提出70%、出席・授業参加20%、最終試験10%」と設定されている時に、課題をおろそかにして最終試験の勉強だけしていては、良い成績は取れないでしょう。
評定の内訳を意識した勉強の時間配分を心掛けましょう。このように、情報管理と時間管理を徹底して、不安なく学業を納めることで、キャリア形成など将来に繋がる活動にも注力できる生活を送りましょう。
まとめ

大学生活におけるテストは、高校と比べて形式も評価方法も多様です。「課題提出」「出席・授業参加」「試験」など、それぞれの科目や教授の方針に応じて対策の仕方を工夫することが求められます。とはいえ、この記事で紹介したように、“早めに情報を集め、過去問を活用し、周囲と協力しながら進めていく”ことで、無理なく対応することができます。
また、授業ごとの評定方法やスケジュールを把握しておくことは、成績だけでなく心のゆとりにもつながります。学業に自信を持つことができれば、インターンシップやアルバイト、サークル活動など、学外でのチャレンジにも余裕を持って取り組めるはずです。
初めての大学のテストに不安を感じるのは自然なことです。しかし、丁寧に準備を重ねることで、少しずつ自分のスタイルが見えてきます。自分に合った勉強法と対策を見つけ、充実した大学生活をスタートさせましょう!