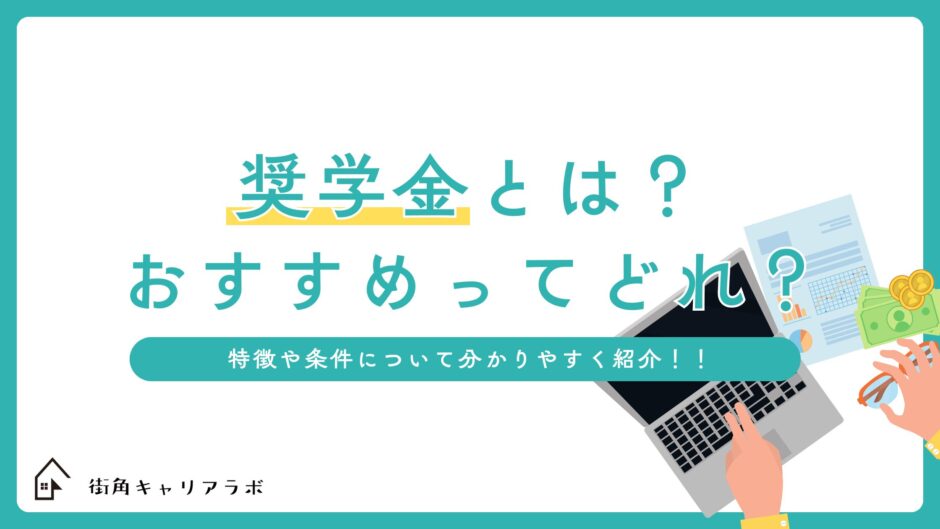突然ですが、皆さんは奨学金を利用していますか?奨学金と聞くと「返済が大変そう」「申請のハードルが高そう」と思う方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、奨学金の種類とそのメリット/デメリットを整理して紹介していきます。
奨学金とは?
そもそも奨学金とは何なのでしょう。日本学生支援機構(以下 JASSO)ではこのような定義がなされています。
奨学金とは、経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資の貸与を行い、また、経済・社会情勢等を踏まえ、学生等が安心して学べるよう、「貸与」または「給付」する制度です。
JASSOが設立されて以降、大半の学生が高校在学中に奨学金を申し込んでいる現状があります。ちなみに筆者もそうでした。また、審査内容は奨学金の種類によって異なりますが、「経済的理由」とあるように申請の際には基本的に家計の状況を証明する書類を提出する必要が多いです。
そして、奨学金は大きく「貸与型」と「給付型」「免除・減免型」に分かれています。貸与型は将来返還義務があるもの、給付型は返還義務がないものという認識で大丈夫です。免除・減免型は、「入学金全額免除」「授業料半額減免」など、学費の一部を払わないで済ませてもらえるものです。
JASSOの奨学金
奨学金の中でもポピュラーなのがこのJASSOのもので、奨学生(貸与型)はおよそ2人に1人といわれています。
また、その種類は以下のようになります。
・第一種:無利息
・第二種:利息がつくパターン
・第一種:特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な方に貸与
貸与型の第一種と第二種の違いは、利息の有無だけではなく、その選考にも違いがあります。
・第二種:第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された方に貸与
※詳しい基準はJASSOのHPを確認してみてください。
また2017年度から始まった給付型は、新制度となり「学業成績等に係る基準(学力基準)」「家計に係る基準 (収入基準・資産基準)」の両方を満たしている方に支給されます。新制度になったことで支給の対象者や支給額が増えました。ちなみに貸与型との併用も可能ですが、貸与を受ける額は制限されます。
メリット
【貸与型】
・第一種:無利息である。
・第二種:他のローンと比べて金利も低く、返済の負担が少ない。在学中は返済不要、かつ利子が発生しない。
やはり第一種が無利息で、返還する額が貸与されたものと変わらないというのは最大のメリットだと思います。また、第二種の金利(1.110%~1.641%【利率固定方式】0.500%~1.100%【利率見直し方式】)は、他の教育ローンの金利(日本政策金融金庫:2.95%【固定】/民間:2.20%~5.90%【変動】3.40%~4.95%【固定】)などと比べて圧倒的に低くなっています。
【給付型】
・返還義務がない
・給付型奨学金の対象となれば、大学・専門学校等の授業料・入学金も免除又は減額される
新制度に変わり、支給の対象者や支給額が増えたこともメリットですね。
デメリット
【貸与型】
貸与型の最大のデメリットが返還しきるのに最長で20年に上ることだと考えられます。また、この奨学金だけでは入学金や授業料を賄うことが難しかったり、貸与開始が大学入学後となり入学金や前期授業料の支払いに間に合わなかったりします。
【給付型】
給付型のデメリットを強いて挙げるならば、自分の在学している学校が制度の対象になっていない場合があることです。自分の大学が対象かどうかはJASSOのHPに記載されているのでぜひ確認してみてください。
また、それぞれに共通するのが申込期間を過ぎたら次の申込期間まで待たなければならないことです。基本的に大学から申請期間などの案内があるので、それを見逃さないようにするのが大切ですね。
給付型奨学金の新制度とは
2019年の大学無償化法がきっかけとなり、2020年4月から給付型奨学金の新制度がスタートしました。以前の給付型奨学金と変わった点は以下のとおりです。
給付型奨学金を申し込める学生枠が増加
給付型奨学金の新制度では、非課税世帯以外も申し込みができるようになり、学生枠が増加しました。以前は生活保護世帯や住民税非課税世帯などが対象でしたが、新制度では「住民税非課税世帯」及び「それに準ずる世帯」までが対象です。
「それに準ずる世帯」とは、家族構成により目安が異なるものの、年収約380万円未満の世帯になります。そのため、住民税非課税世帯からギリギリ外れたラインにいた方でも、給付型奨学金を申し込めるようになっています。さらに、給付型奨学金の新制度では「授業料・入学金の免除や減額」もセットになっているため、費用面を気にせず安心して学業に励めます。
支援される金額が増額
給付型奨学金の新制度では、支援される金額も増額しています。
独立行政法人 日本学生支援機構が発行する「リーフレット」によると、「年収270万円未満(住民税非課税世帯)の第一区分は上限額」「年収300万円未満の第二区分は上限額の2/3」「年収約380万円未満の第三区分は上限額の1/3」の支給となっています。
たとえば、第一区分の住民税非課税世帯(年収270万円未満)に該当する学生で国公立の大学・短期大学・私立に通った場合の給付型奨学金の支給月額は、自宅生だと29,200円、自宅外生だと66,700円となります。
・進学資金シミュレーター
必要な項目を入力することで、自分がどの収入基準に該当するかどうかの目安を確認できますhttps://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/document/shogakukin-simulator.html
(実際の選考結果とは 必ずしも一致しません)
給付型奨学金の新制度で気をつけること
給付型奨学金の新制度には、注意したい4つのポイントがあります。
すべての学校が対象ではない
まず1つ目が「すべての学校が対象ではないこと」です。支援の対象となる大学・短大・高専・専門学校に該当しないと給付型奨学金の新制度を利用することができません。
なお、給付型奨学金の対象校に該当するかは文部科学省のHPより確認できます。
受給額に制限がある場合も
給付型奨学金の新制度は、日本学生支援機構の「入学時特別増額貸与奨学金」「第一種学資貸与金(無利子奨学金)」「第二種学資貸与金(有利子奨学金)」と併用することが可能です。
しかし、支援バランスを維持するため、第一種学資貸与金(無利子奨学金)に関しては受給額に制限がある場合もあります。第二種学資貸与金(有利子奨学金)に関しては利用額の制限はありません。
なお、日本学生支援機構以外でも給付型奨学金の新制度と一緒に利用できる場合があるものの、受給額に制限が出てくる可能性があります。そのため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
入学前にお金が振り込まれるわけではない
これから初めて給付型奨学金の新制度を利用する高校生の場合ですが、入学前にお金が振り込まれるわけではないことを念頭に置いておきましょう。
給付型奨学金が振り込まれるのは、入学後の4月か5月です。進学先によっては、入学する前に入学金・授業料の納付を求められることがあります。事前にお金を用意していないと支払うことが難しくなってしまうため、入学前に準備しておかなければなりません。
なお、支払いが完了したら入学後に手続きし、減免相当額が還付される仕組みとなっています。
すでに支払った入学金などは減免されない
在学中に給付型奨学金の新制度を利用する場合は、すでに支払った入学金などは減免されないので注意しましょう。現行の給付型奨学金を受けていて引き続き在学する方は、新制度に切り替えることはできます。ただし、無条件に切り替えられるわけではなく、諸要件を満たし審査に通ると利用が可能です。
大学の奨学金
大学には、JASSOの奨学金とは別に大学独自の奨学金制度を運営しているところがあります。これは貸与型と給付型に加えて免除・減免型に分かれています。この免除・減免型は返済の必要がないため、採用条件が厳しめであることも特徴です。
メリット
メリットは給付型の割合が高いことです。これは大学が後援会からの助成金や大学基金を元に奨学金制度を運営していることが多いためだと考えられます。また、大規模な私大では学部ごとに奨学金が用意されていることもあります(中央大学など)。
デメリット
一方でデメリットは、採用人数が少ないことと前年度の成績が大きく影響することです。採用人数が少ないからこそ倍率が高くなり、より良い成績を収めることが求められることになります。また、成績だけでなく経済事由が条件に入っているものもあるので、自大学がどのような条件の奨学金なのかを確認しておきましょう。
地方自治体・民間奨学財団などの奨学金
最後に、地方自治体や企業などが後援する民間団体の奨学金制度も確認しておきましょう。
・地方自治体:市や県の奨学金制度。貸与型(無利子)、給付型、貸与+給付型がある。
・民間団体:あしなが育英会(貸与型)や新聞奨学金(貸与+給付型)など。給付型もある。
地方自治体のものは、無利子による一定金額の月額貸与が多いです。貸与の条件には本人または保護者がその地方自治体に居住しているか、その地方自治体の出身であることが挙げられます。
また、民間団体のものは採用人数は決して多くはありませんが、成績優秀者や特定の技能に秀でた者などを対象に、給付型の奨学金があります。
メリット
【地方自治体】
無利子であることがメリットで、借りた額と同じ額を返せば良いので返済の負担が少し軽くなります。
【民間団体】
企業などが後援する民間団体の奨学金制度が数多くあることがメリットです。「○○育英会」「△△奨学会」といった名称となっているものが多いです。それと同時に、このパターンは給付型の割合が高くなります。
デメリット
【地方自治体】
日本学生支援機構や他の奨学金との併用が認められない場合も多いことがデメリットに挙げられます。さらに、全ての地方自治体がこの種の奨学金制度を実施しているとは限らず、内容についても個々に異なっている点には注意が必要です。
【民間団体】
大学のものと同様に採用人数が少なく、学業成績基準なども高く設定されていることがデメリットです。また、入学前の時点では確実に利用できるかどうかは分らないので、あくまでも「学費を工面する方法の一つ」として考えておくことをお勧めします。
さて、今回は奨学金の種類とそのメリット/デメリットを見てきましたがいかがでしたでしょうか? 種類によって申請できる条件や貸与/給付される額が変わってくるので、今回気になったものがあればぜひ皆さん自身でも調べてみてください
参考サイト:
https://financial-field.com/living/2019/09/04/entry-5579
教育ローンのおすすめ人気ランキング【2025年3月徹底比較】 | マイベスト
エビデンス:
https://www.mext.go.jp/kyufu/assets/file/20200305_mxt_kouhou02_01.pdf